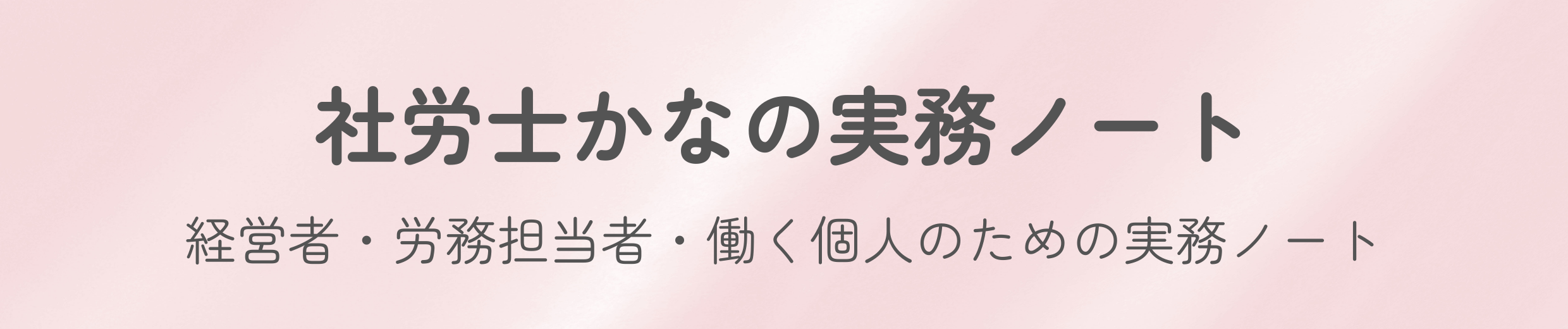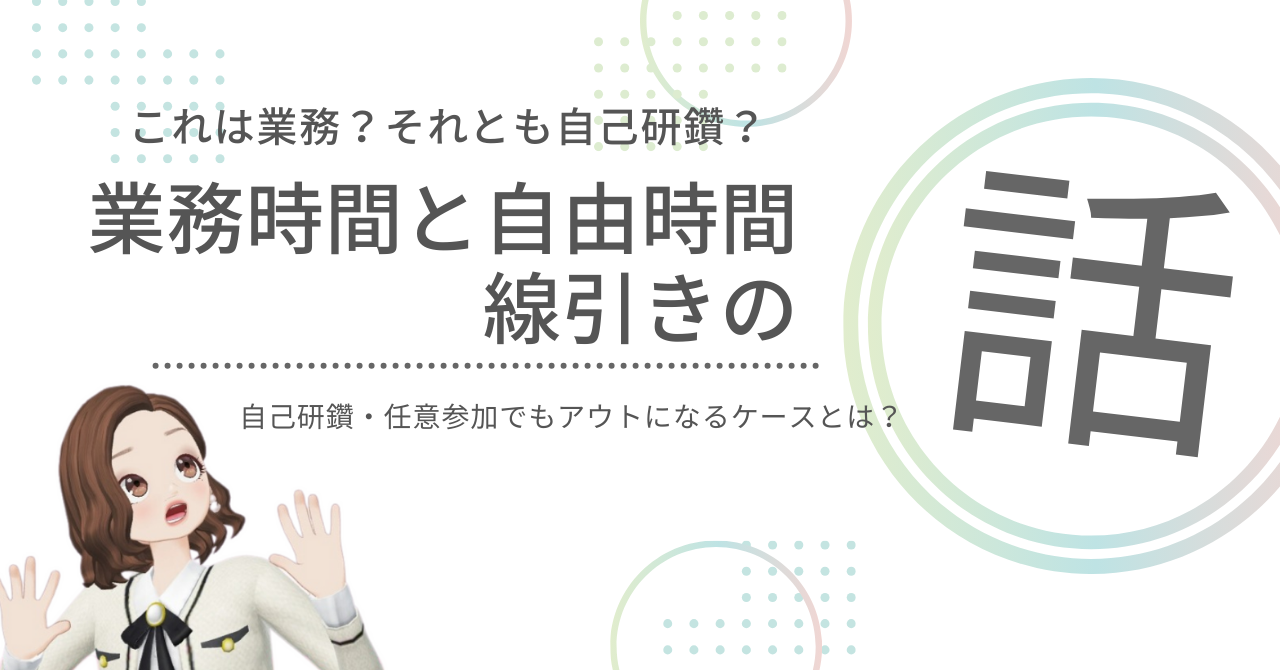「業務時間後に、社員が自主的に勉強していたんです」
「研修は任意参加なので、残業代は払っていません」
──そんな企業の説明、実は裁判所では通用しないケースが多いのをご存じですか?

特に問題になるのは、
「自己研鑽」として行っていた勉強や研修が、
裁判所から“労働時間”と認定されるケースです。
実際に、企業が残業代請求で敗訴した判例もあります。
今回は、裁判所が“線を引いた基準”をもとに、
「どこまでが労働時間とされるのか?」をやさしく解説します。
第1章|何が問題になるのか?──“労働時間”の定義とは
労働時間とは、
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間
と定義されています(最三小判 平成12年3月9日)。
ここで重要なのは、「会社が明示的に命じたかどうか」だけでなく、
「実質的に参加を余儀なくされていたか」や
「会社の評価・査定に影響するかどうか」なども含めて、
“黙示の指揮命令”があったか否かが問われるという点です。
つまり、形式的に「自由参加」としていても、
実態が強制であればアウトなのです。

第2章|実は“残業代の対象”だったケース
たとえばある会社では、
就業後に「任意の勉強会」が行われていました。
資料は会社から提供され、
社内の会議室を使い、上司も参加していた──
しかも、昇進試験にその内容が出題されるなど、
人事評価に直結していたのです。
このケース、裁判所は明確に「労働時間に該当する」と判断しました。
つまり企業側の説明である
「社員の自主性に基づく学習」は否定され、
未払い残業代の支払いが命じられたのです。

第3章|裁判所はここを見る!線引きポイント5つ
「これは自主的な学びだから残業代は発生しない」と企業が判断しても、
それが通るかどうかは裁判所の視点次第です。
裁判所は、
以下のようなポイントを見て
「それが労働時間にあたるかどうか」を判断しています。
① その内容は業務と関係あるか?
まず最初に見られるのは、
研修や勉強の内容が業務と直接関係しているかどうかです。
たとえば、接客マナーや商品知識、営業手法など
「現場ですぐに使うもの」は“業務の一環”と判断されやすくなります。
② 上司や会社からの指示があったか?
「出ても出なくてもいい」と言いつつ、上司が声をかけてきたり、
「参加して当然」という空気があった場合、
それは黙示の指示とみなされる可能性があります。
形式的には自由でも、実質的に強制されていた場合はアウトです。
③ 出欠や評価に関係していないか?
参加の有無が人事評価や昇進に影響する場合、
事実上の業務指示と受け取られます。
「自由参加」と言いながら
「参加しないと昇進できない」のような仕組みは、
明確に労働時間とみなされます。
④ 実施のタイミングは勤務時間に近接していないか?
就業直後や、昼休み中、あるいはタイムカードを切った“直後”など、
勤務時間に極めて近い時間帯に実施されていると、
「実質的に勤務の一部」とみなされやすくなります。
⑤ 場所や資料は会社が提供していないか?
勉強や研修が会社の会議室で行われ、
資料も会社から配布されている場合は、
企業の関与が強く、労働時間と認定される傾向があります。
逆に、自宅で私物の資料を使って自主的に学習しているなら、
自己研鑽と認められやすいでしょう。

第4章|企業がやるべきリスク回避策
働き方改革や副業解禁が進む中で、
「学ぶ社員が増える=企業としても支援したい」という動きが広がっています。
しかし、そこで会社が少しでも評価制度と絡めたり、
上司が参加を“期待”したりすると、
“労働時間とみなされる可能性”が一気に高まります。
さらに、SNSや口コミで情報が共有されやすい時代になり、
1人の退職者から未払い残業代の相談が入れば、
“ドミノ請求”のリスクもあります。

第5章|リスクを減らすために企業がすべきこと
- 「任意参加」であることを明文化し、記録に残す
- 出欠確認や評価との紐付けを避ける
- 場所・設備・資料を会社が提供しない工夫も有効
- 定期的に制度と運用のズレを確認する
社内勉強会は企業文化の一部として大切ですが、
法的リスクと隣り合わせです。
「つもり」ではなく、「実態」で判断されることを忘れてはいけません。
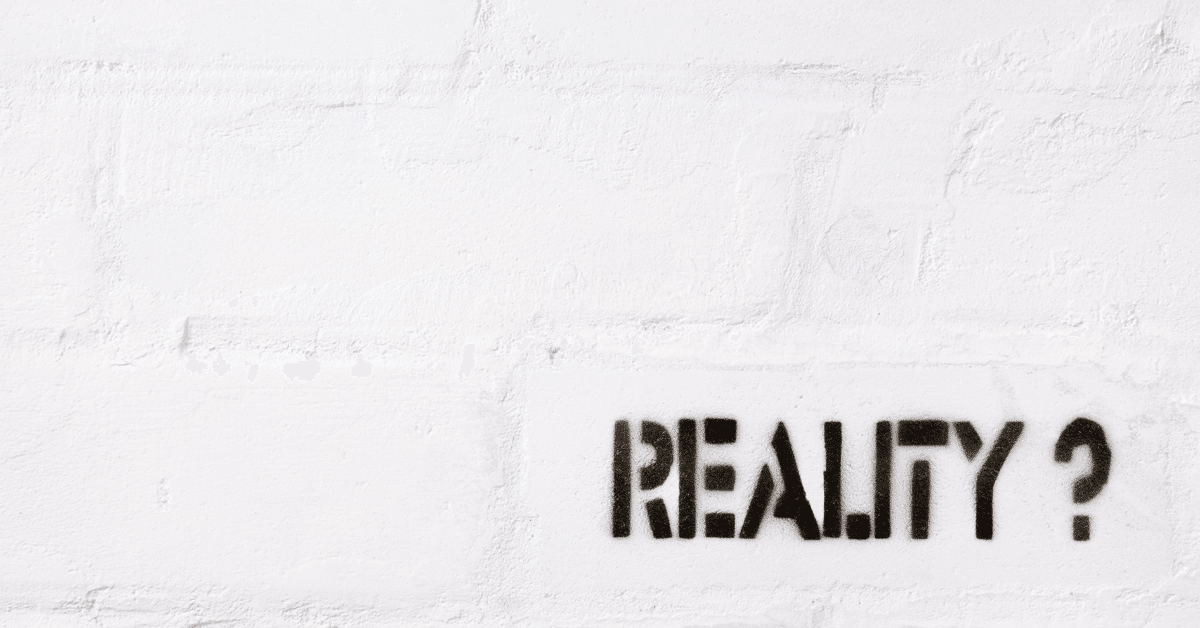
まとめ|“善意”が“違法”に変わる前に。
社員の成長を想って行った取り組みが、
「残業代未払い」「訴訟リスク」につながってしまった──
そんな悲しい話、実は珍しくありません。
企業ができるのは、
「これは自己研鑽だから大丈夫」ではなく、リスクベースで判断すること。
ルールを整え、現場と制度のギャップをなくすことです。

ご相談はこちら
「うちのケースは大丈夫?」「制度を見直したい」
そんなご相談がありましたら、下記LINEからお気軽にご連絡ください。