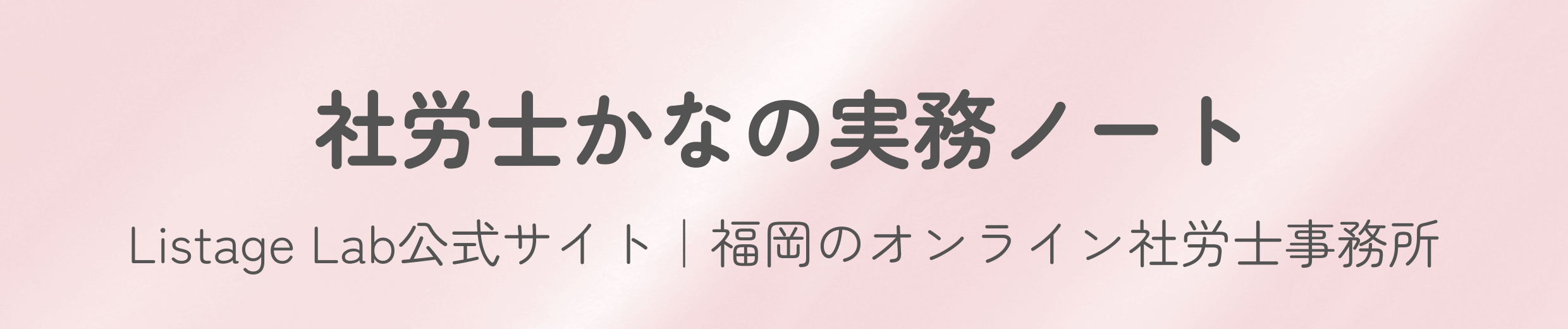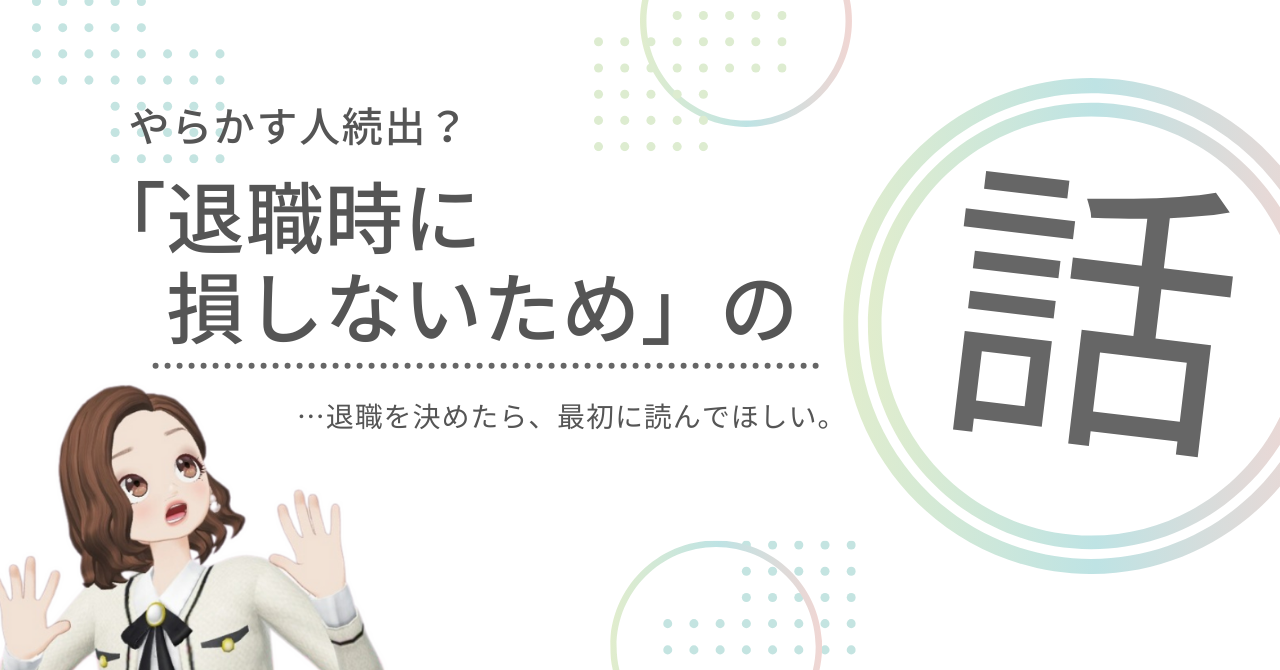こんにちは、社労士のかなです。
これまで多くの方の退職相談や手続きをサポートしてきた中で、
いつも感じることがあります。
「それ、先に知ってさえいれば損しなかったのに…!」

退職は人生の節目ですが、
意外と“やるべきこと”を知らずに終えてしまう人が本当に多い。
そしてその結果、
「失業手当が受け取れない」
「保険証が使えなかった」
「住民税の督促状が届いた」…なんてことが、
あとからドッと押し寄せてきます。
そんな“退職直前の落とし穴”を回避するために、
今回は 「退職前にやっておきたい5つのこと」 をまとめました。
これから辞める予定のある方、
または過去に“やらかした”ことがある方も、
ぜひ最後まで読んでみてください。
第1章|有休は使い切らないと損!
「退職するんだから、有給なんて使わず最後まで出勤してよ」
と言われた経験はありませんか?
でも、有給休暇は“会社にお願いして取るもの”ではありません。
労働者に認められた「時季指定権」というれっきとした権利です。
つまり、有休が残っていれば、
「〇月〇日から退職日までは有給を消化します」
と自分で宣言することができるのです。

もちろん会社側にも「時季変更権」はありますが、
退職日が決まっている場合、
それを理由に有休を拒むのは原則としてNG。
実際、多くの方が退職日まで有休をフル消化して辞めています。
辞め方は自分で選べる。
「出勤して気まずく終わる」より、
「有休でフェードアウトして心穏やかに終える」方が、
きっと気持ちよく次に進めます。
第2章|「離職票はもらえますか?」は必ず聞いて
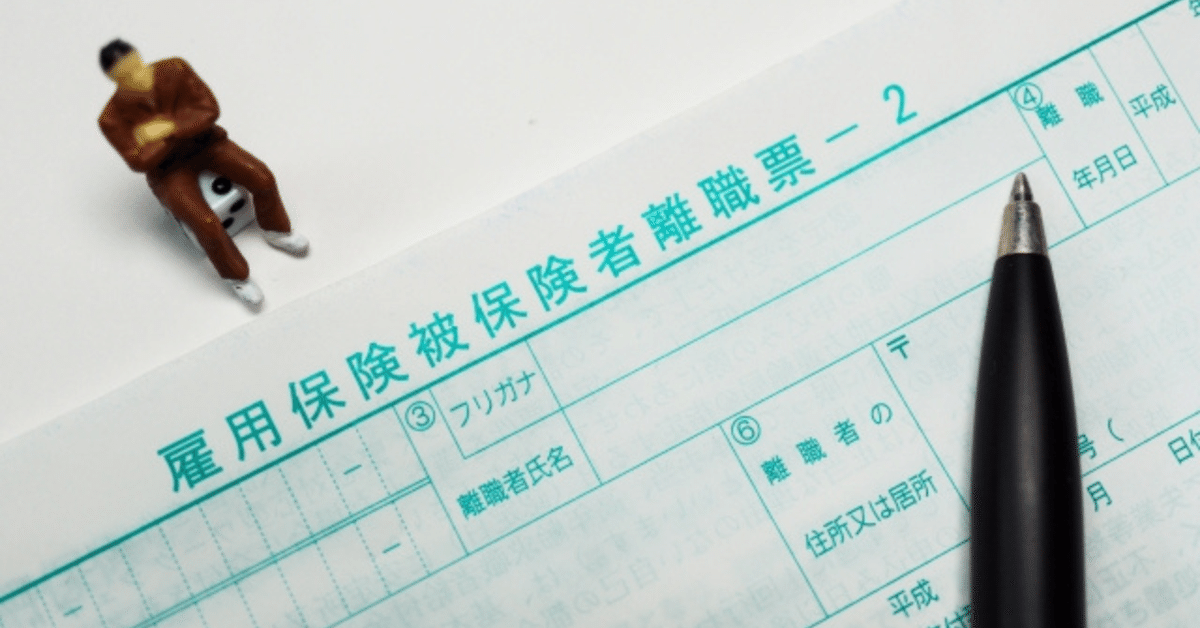
なぜかというと
離職票は、本人が希望してはじめて発行されるから。
そう、会社には“自動的に発行する義務”はないんです。
離職票は、雇用保険(失業手当)を受給する際に必要な重要書類。
ハローワークで手続きする予定がある人は、退職前に必ず
「離職票を発行してください」
と伝えておきましょう。
さらに、「いつ頃発送されるか?」も聞いておくと安心です。
多くの場合、退職後10日〜2週間ほどかかるため、
引越しなどがある人は特に注意。
忘れていて困るのは、いつも自分。
退職時の書類こそ、きちんと準備しておきましょう。
第3章|健康保険の切り替えは“時間との勝負”
退職した瞬間、健康保険証は“使えなくなります”。
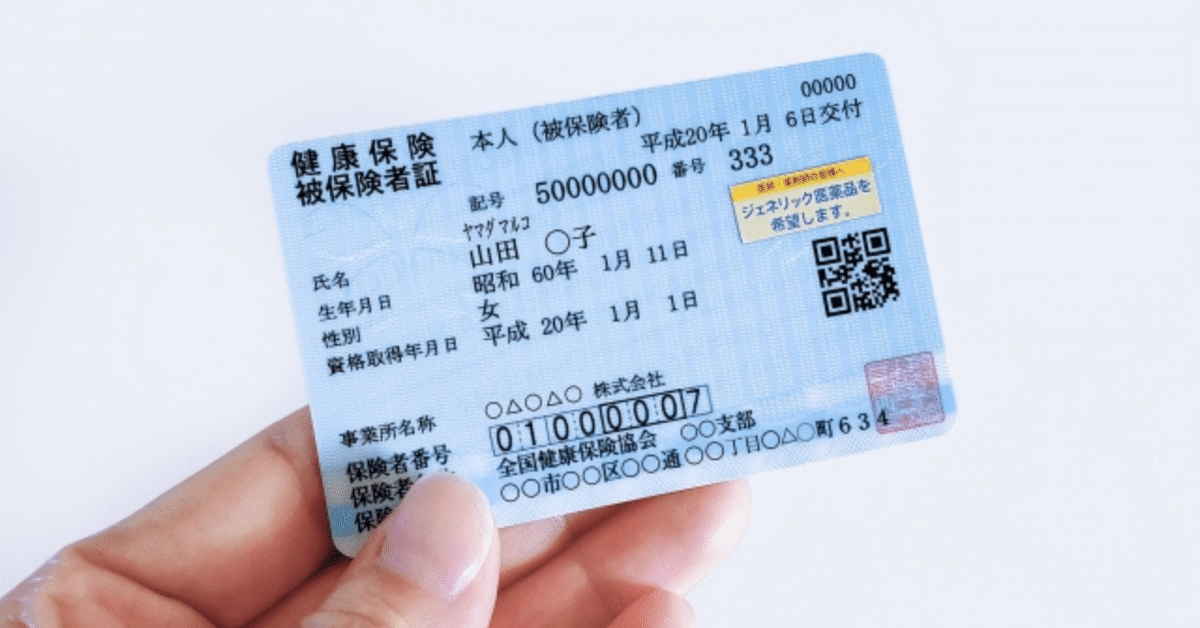
「え、まだ有効期限あるし…」と思って病院に行くと、
窓口で“全額負担”になるケースも。
退職後の健康保険は、次の3択になります。
- 配偶者の扶養に入る(条件あり)
- 任意継続(最大2年、前職の健康保険を継続)
- 国民健康保険に加入する(市区町村で手続き)
このうち、
任意継続は「退職後20日以内の申請が必要」という縛りがあります。
しかも、1日でも遅れると受け付けてもらえません。
つまり、選択と行動がめちゃくちゃ早く求められるのです。
どれが最適かは、保険料や家族構成によって変わります。
退職前にシミュレーションしておくことが大事です。
第4章|もらうもの・返すもの、チェックしてる?
退職直前って、ちょっと気まずいですよね。
だからこそ、やるべきことが雑になりがち。
でも、「退職時にもらうもの・返すもの」リストは超重要。

もらうべき書類
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 離職票(希望者)
- 健康保険資格喪失証明書(任意継続の申請に必要)
返却するもの
- 健康保険証
- 社員証・IDカード
- 制服や社用携帯などの貸与品
特に源泉徴収票は、年末調整や確定申告で必須になります。
後から「あれ、もらってなかった…」となると、
会社に連絡を取るのも気まずいし、時間もかかる。
円満退職を目指すなら、最後の最後まで“きっちり”が基本です。
第5章|「年金・住民税の手続き忘れ」に注意
退職後、多くの人が見落としがちなのが「年金」と「住民税」。

とくに「しばらく働かない」「フリーランスになる」
という人ほど、注意が必要です。
退職後の基本アクション
- 国民年金への切り替え(14日以内)
- 住民税の納付方法の確認(原則“普通徴収”になる)
これを忘れていると…
「年金未納通知が届いた」
「住民税の延滞金を請求された」
というパターンは本当に多い。
住民税は、退職時点で“まだ未納の前年度分”があることが多く、
一括で支払いが求められるケースも。
金額は数万円〜10万円超になることも…。
退職後は「健康保険」だけじゃなく、
“3点セット(保険・年金・住民税)”で確認するのが基本です。
おわりに|「辞め方」が、次の人生をつくる
退職って、ただ“仕事を辞める手続き”ではありません。
「次の人生を、どんな気持ちでスタートできるか」を左右する、
大きな分岐点です。
だからこそ、
- 有給をちゃんと消化して
- 書類の受け渡しを丁寧にして
- 保険・年金・税金の手続きも抜け漏れなく
この“5つの準備”が、損しない辞め方をつくります。
「退職は新しい始まり」。
そのスタートを、後悔で曇らせないために。です。

「これ、会社の対応ちょっと変じゃない?」
「自分のケースはどうなるんだろう…?」
そんな不安や疑問があれば、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
社労士として、あなたの「働く」をサポートします。