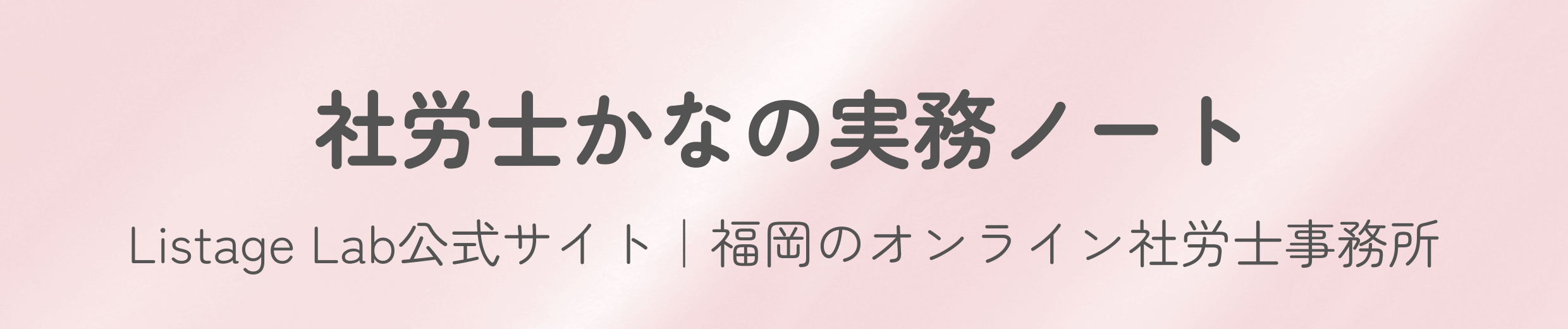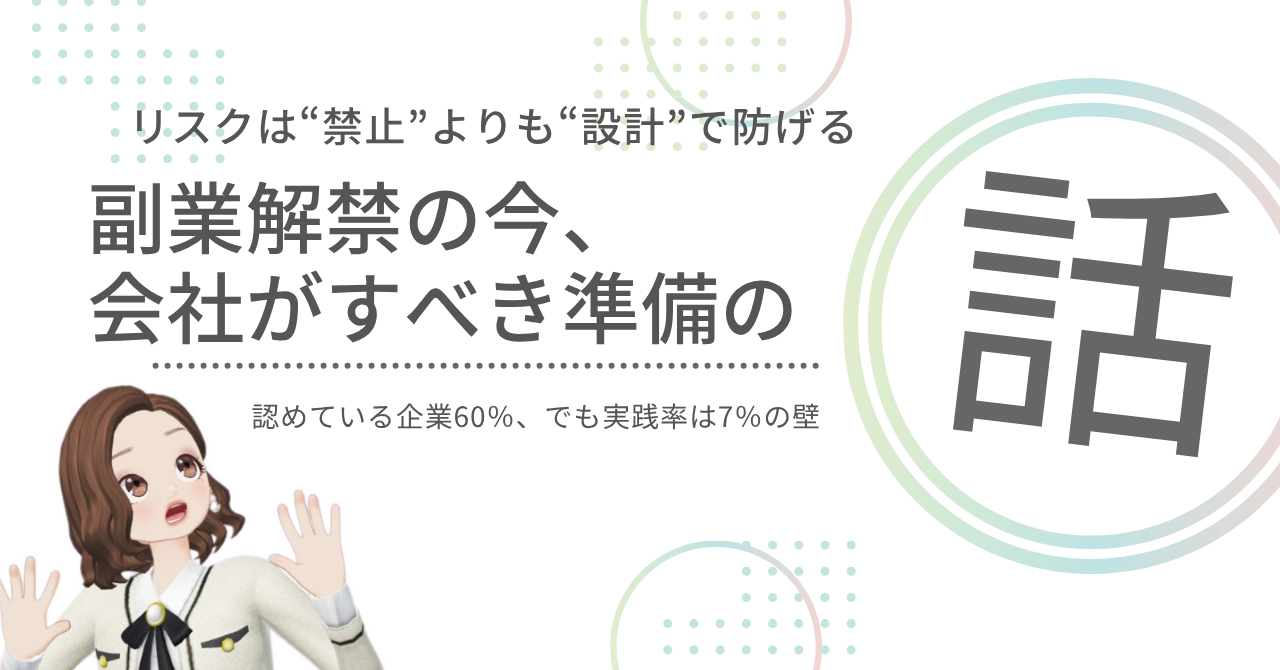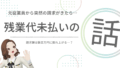「最近、社員が副業しているようなんです。これって大丈夫なんでしょうか?」
社労士として経営者から最も多く受ける相談のひとつが、このテーマです。
働き方改革や人手不足、副業解禁の流れを受けて、
いま多くの企業が“社員の副業”に向き合わざるを得ない時代になりました。
ただ、現場ではまだまだ「禁止しておいたほうが安全では?」という声が根強いのも事実。
しかし実務的に見れば、副業は禁止よりも「設計」こそが最大の防御策です。
今回は、社労士の立場から、
副業をめぐるリスクとその具体的な制度設計について整理してみます。
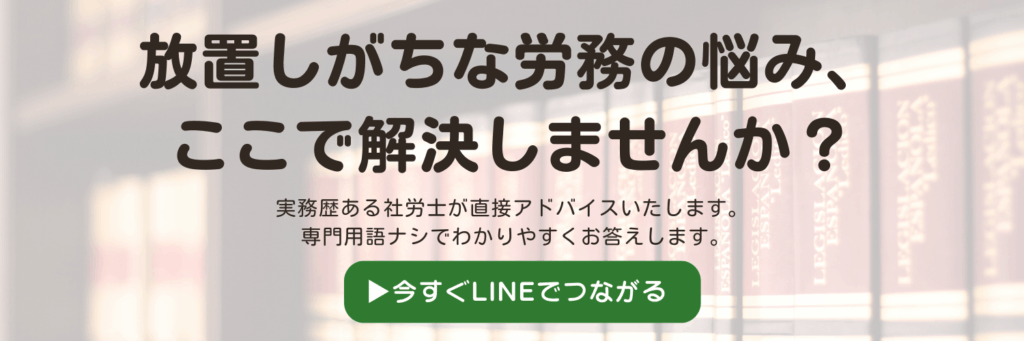
第1章|「副業=リスク」という思い込みが生む本当のリスク
厚生労働省が2022年に改定した
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、
明確に「原則容認」へと方向転換が示されました。
しかし中小企業の現場では、
依然として「副業はトラブルのもと」という固定観念が根強い。
けれども実際は、禁止しても水面下で副業を行う社員は減りません。
その結果、
勤務時間の通算・情報漏えい・健康管理などの実態が把握できず、
企業側が責任を問われるリスクが高まります。
つまり、副業を禁止することこそが「管理できないリスク」を生むのです。
だからこそ今、経営者に求められているのは、
“禁止”から“制度設計”への転換です。
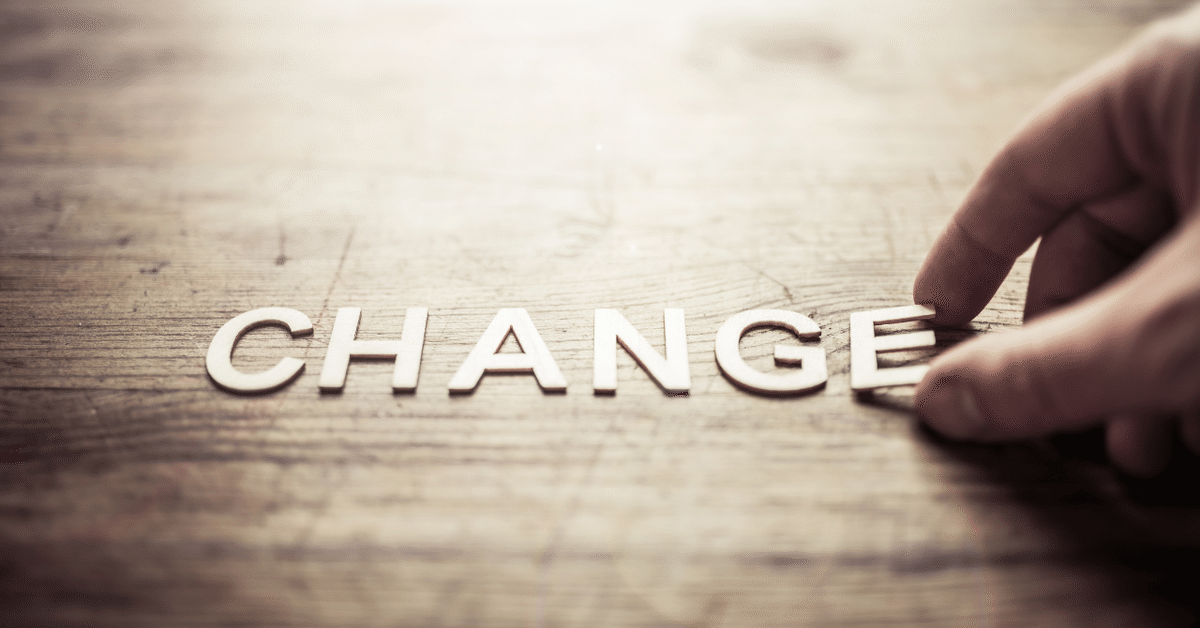
第2章|労働時間の通算——副業リスクの中で最も見落とされるポイント
副業を認める際、
まず確認すべきは労働基準法第38条「労働時間の通算」です。

これは、
ひとりの労働者が複数の会社で雇用契約を結んでいる場合、
すべての勤務時間を合算して労働時間を判断するという規定です。
たとえば、
A社で1日8時間勤務し、B社でも3時間働いた場合——
その3時間は法定時間外労働として扱われ、
A・B両社が協力して残業時間管理を行う必要があります。
この原則を理解せずに副業を許可すると、
「知らないうちに法定時間外労働」「未払い残業」といったトラブルに直結します。
💡実務上の対策
- 副業は原則“業務委託契約”とし、雇用契約との区別を明確にする。
- 就業規則に「副業を行う場合は契約形態・労働時間を申告する義務」を定める。
- 申告フォームを整備し、36協定との整合性を定期的に確認する。
第3章|情報漏えい・競業避止義務——“感覚”ではなく“条文”で守る
もうひとつの大きな論点が「競業」と「情報漏えい」です。
特に営業・開発・コンサルティング職など、
知識や取引先情報を扱う職種ではトラブルになりやすい部分です。
「どこまでが競業行為なのか?」
「副業でSNS発信をしても問題ないのか?」
これを感覚で判断すると、後で取り返しがつきません。
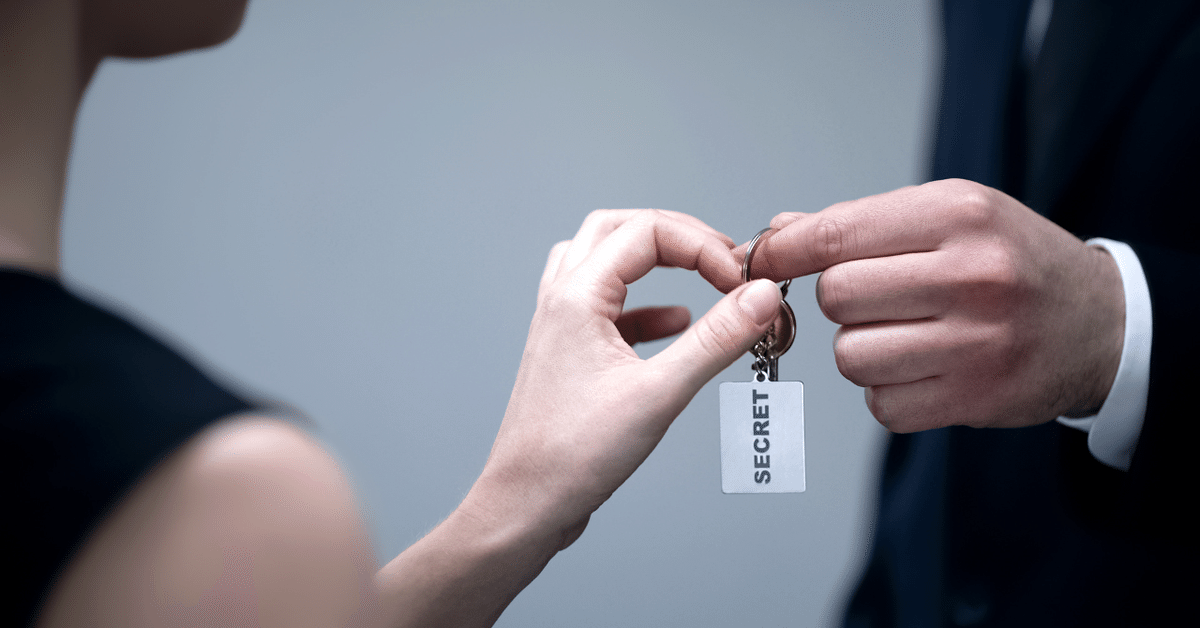
労働契約法第3条・民法第415条などの法的根拠を踏まえて、
就業規則・誓約書・副業届に具体的な禁止行為を明文化しておくことが必須です。
【明文化の一例】
従業員は、会社の許可なく、会社と競合する業務または会社の信用を害する行為を行ってはならない。
副業・兼業を行う場合は、事前に届出書を提出し、会社の承認を受けるものとする。
懲戒処分を行う場合、
この「事前に明示した条文の存在」が非常に重要です。
逆に、曖昧なルールのままでは懲戒の正当性を主張できず、
労働審判などで不利になるケースもあります。
第4章|社会保険・税務の仕組みを“経営側”も理解しておく
副業トラブルの多くは、制度の理解不足から起こります。
特に「社会保険」「住民税」の仕組みは経営者側も把握しておくべきです。
よくあるケース
- 副業先でも週20時間以上勤務 → 社会保険加入義務が発生(106万円ライン)
- 扶養内勤務だったが副業収入で年130万円を超過 → 扶養喪失で国保加入
- 確定申告を行わず住民税が本業に合算 → “副業バレ”トラブル発生
経営者としては、
こうした制度上の“連鎖反応”を理解しておくことが、
社員との信頼関係を守る第一歩になります。
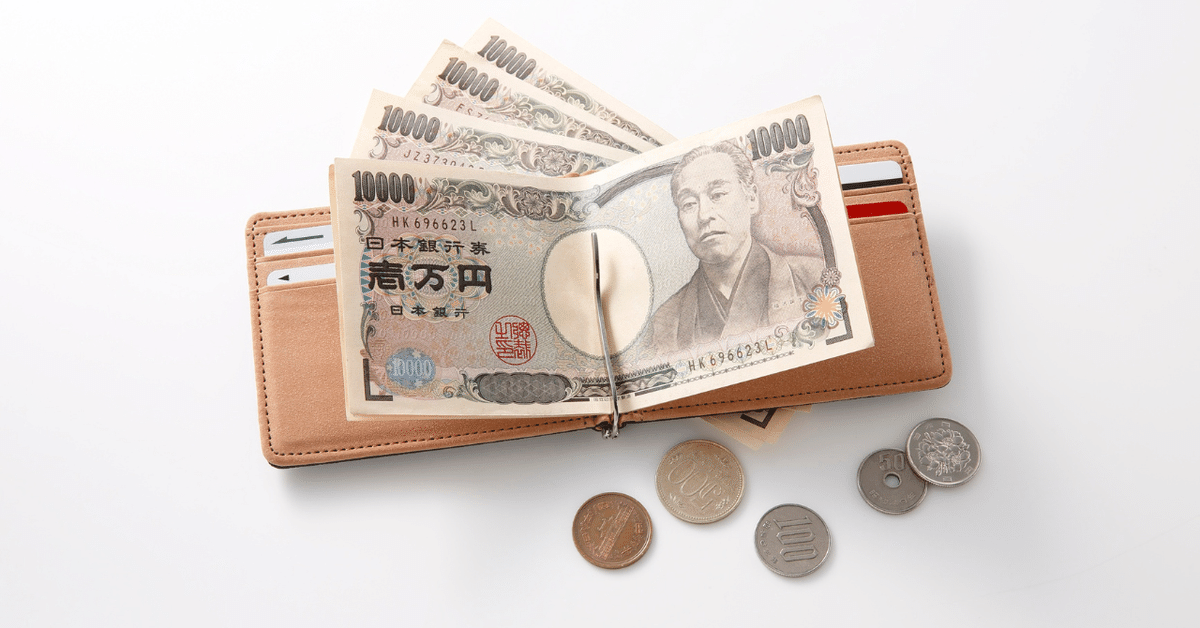
💡実務ポイント
- 税理士・社労士と連携し、住民税の通知経路を確認
- 扶養・社保の要件を明文化して社員に説明
- 「虚偽申告・無届副業は懲戒対象」と就業規則に明記
第5章| 就業規則を“禁止ルール”から“信頼ルール”へ
多くの企業では、
副業に関する条文が平成初期のまま更新されていません。
その結果、
現状に合わない“副業禁止”規定が残ったままになっているケースが非常に多いです。
しかし実務上は、「禁止」ではなく“申告・許可制”が合理的です。
社員が正直に申告できる環境をつくることこそ、
労務リスクを可視化し、管理可能な状態にする第一歩です。
【就業規則改定のステップ】
- 現行ルールの棚卸し:副業条文の有無・内容を確認
- 届出・承認制度の設計:申請書・判断基準・許可範囲を整備
- モニタリング体制の構築:年1回の労働時間・社保確認を義務化
副業ルールを整えることは、労務管理の“土台整備”でもあります。
ここを怠ると、トラブル発生時に経営者が防御できません。

第6章|「副業を許可する会社」から「副業を育てる会社」へ
副業は、社員の自由の象徴ではなく、
企業と社員が“責任を共有する仕組み”です。
禁止して守る時代から、整備して共に育てる時代へ。
経営者がこの発想を持てるかどうかが、組織の競争力を左右します。
実際、副業を制度化した企業ほど——
- 自立的な社員が増え、マネジメント負担が軽減
- 他業界の知見が社内に還元され、イノベーションが生まれる
- 「社員を信頼している会社」として採用力が向上
といった効果が出ています。
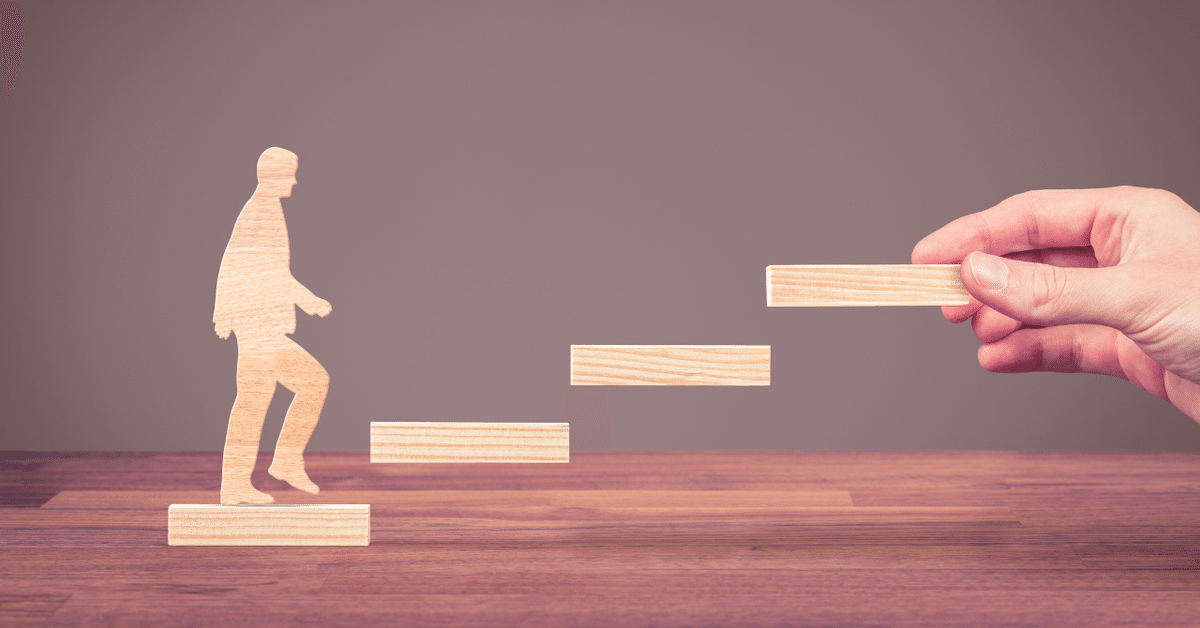
まとめ|副業制度は“経営リスク対策”であり、“信頼経営”の礎
副業を認めるか否かは、単なる人事判断ではありません。
それは、会社が「社員をどう信じ、どう育てるか」という経営の意思表示です。
社労士として言い切れるのは——
副業制度を正しく設計できる会社は、
労務リスク管理能力が高い会社であるということ。
そして、労務リスクをコントロールできる会社は、
変化の激しい時代にも揺るがない「信頼経営」を築けます。
“副業を恐れない会社”こそが、“人を活かす会社”になる。
ルールを整え、信頼で運用することが、次の時代のスタンダードです。
「うちの会社の場合はどうすればいい?」という疑問があれば、
ぜひお気軽にご相談ださい!
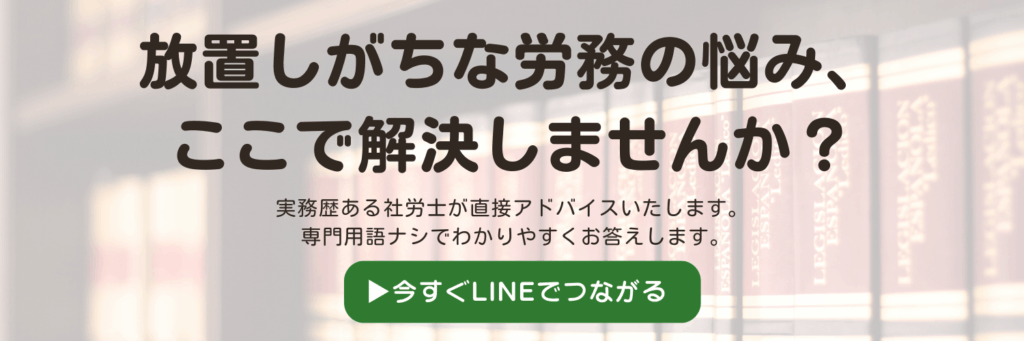
記事を読んで「この人、どんな社労士なんだろう?」と思った方は、
ぜひこちらも覗いてみてください。