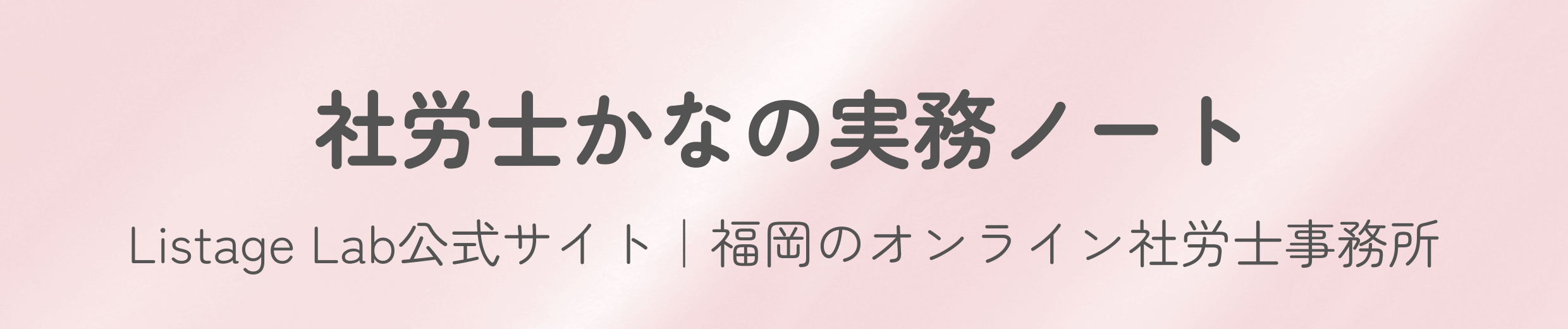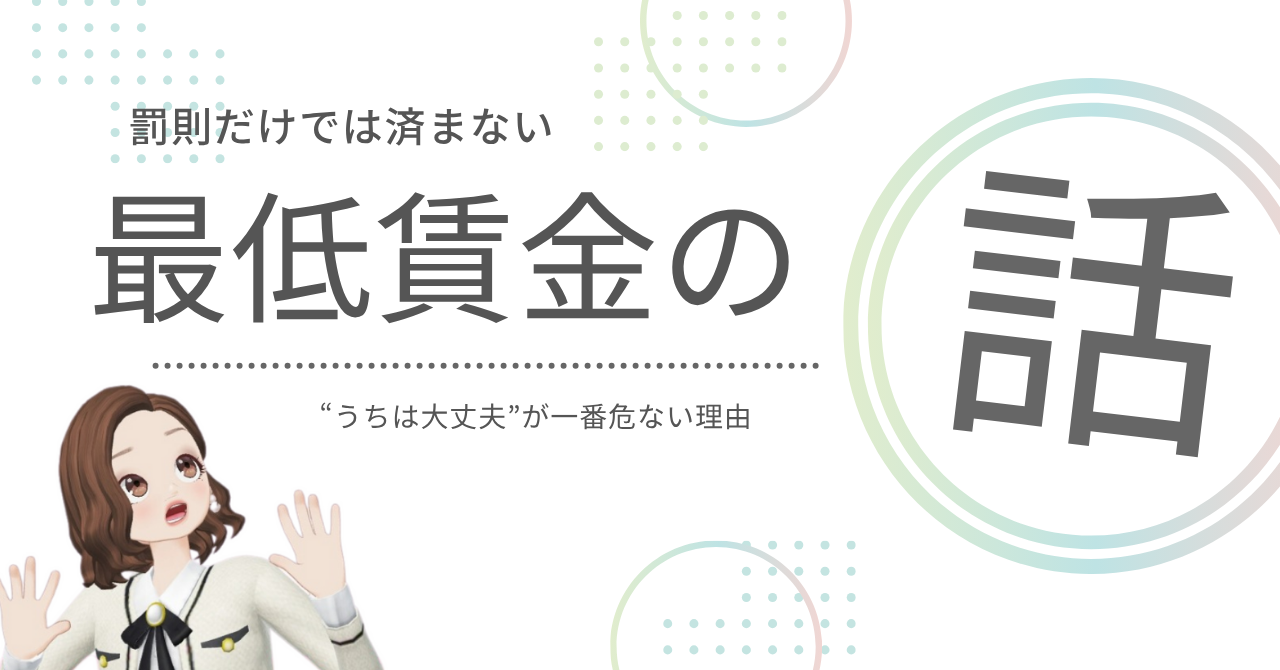毎年のように上がる最低賃金。
「たった数十円の話でしょ」と思っていませんか?
実は、最低賃金を下回る賃金で従業員を雇うと、
罰則・是正勧告・助成金停止・信用失墜といった、
経営に直結するリスクを伴います。

しかも、
「うちは月給制だから関係ない」と油断している会社ほど、
時給換算で“割れていた”というケースが多いのが実情です。
この記事では、社労士の視点から
最低賃金を下回ったときに起こる現実と、
1,500円時代に備えるための実務対応を解説します。
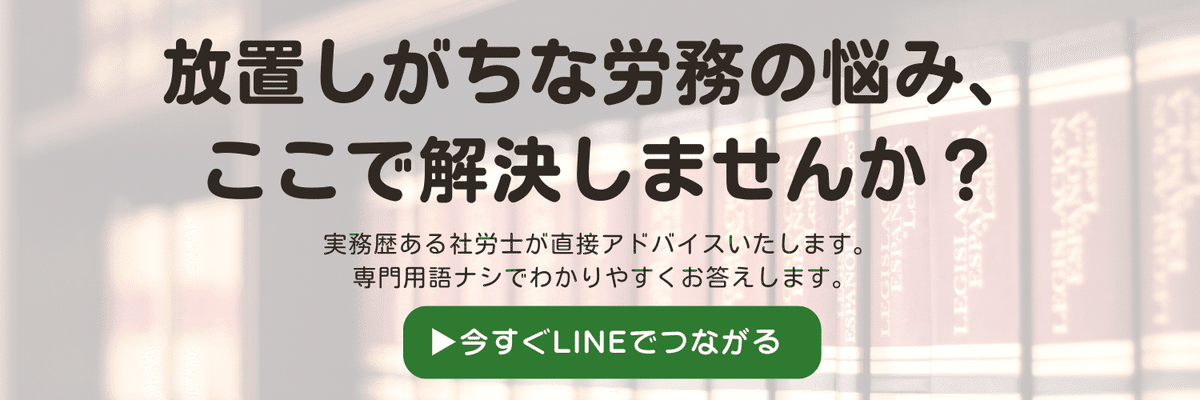
第1章│最低賃金を下回ったらどうなるのか
最低賃金法第4条では、
使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
と定められています。
違反した場合、最低賃金法第40条により、
罰則:50万円以下の罰金
が科されます。
さらに、労働基準監督署の調査で発覚すれば、
過去に遡っての差額支払い+是正勧告(指導票)が行われます。

よくある“割れ”のパターンは次の通りです。
1️⃣月給制社員が時給換算で割れていた
2️⃣固定残業代込みで計算してしまっていた
3️⃣基本給に含めてはいけない手当を加算していた
4️⃣改定時に契約更新が漏れていた
月給制でも対象になります。
1か月の所定労働時間で割り戻して時給換算した際、
地域の最低賃金を下回れば違反です。
第2章│金銭だけではない「信用リスク」の怖さ
罰金や差額支払いだけでは終わりません。
最低賃金割れは、会社の信用と経営基盤に影響します。
(1)助成金・補助金の支給停止
キャリアアップ助成金・人材開発支援など、
最低賃金法違反があると
申請不可または返還命令になる場合があります。
(2)監督署による企業名の公表
悪質なケースでは、
企業名が厚生労働省HPに掲載されます。
一度公表されると、検索結果に長期間残り、
採用・取引・融資などに影響します。
(3)SNS・求人サイトでの炎上
最近は、社員がSNS上で
「うちの時給、最低賃金以下」と投稿し炎上する例も。
求人票の誤記(最低賃金改定前の金額のまま掲載)でも、
ハローワーク経由で通報されることがあります。
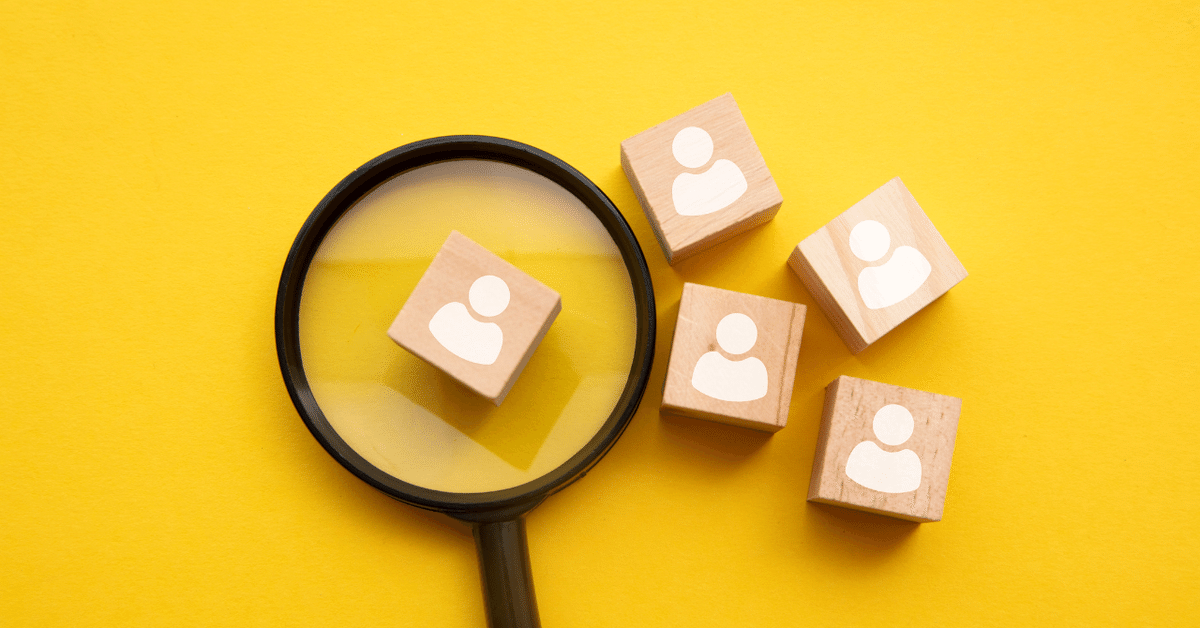
第3章│最低賃金割れを防ぐための3つの整え方
最低賃金対応は“毎年のイベント”ではなく、「制度の健康診断」です。
チェック①:時給換算を正しく
月給 ÷ 所定労働時間(173.8hなど)で算出。
残業代・通勤手当・家族手当などは除外して比較します。
チェック②:手当構成を明確に
「何が賃金に含まれるか」を就業規則に明記。
固定残業代がある場合は、
みなし時間・金額・超過時の扱いを明確化。
チェック③:契約書・賃金テーブルの更新
賃金表や昇給ルールを改定しないまま放置していないか?
毎年の改定に合わせて、契約更新・通知書改定を行いましょう。
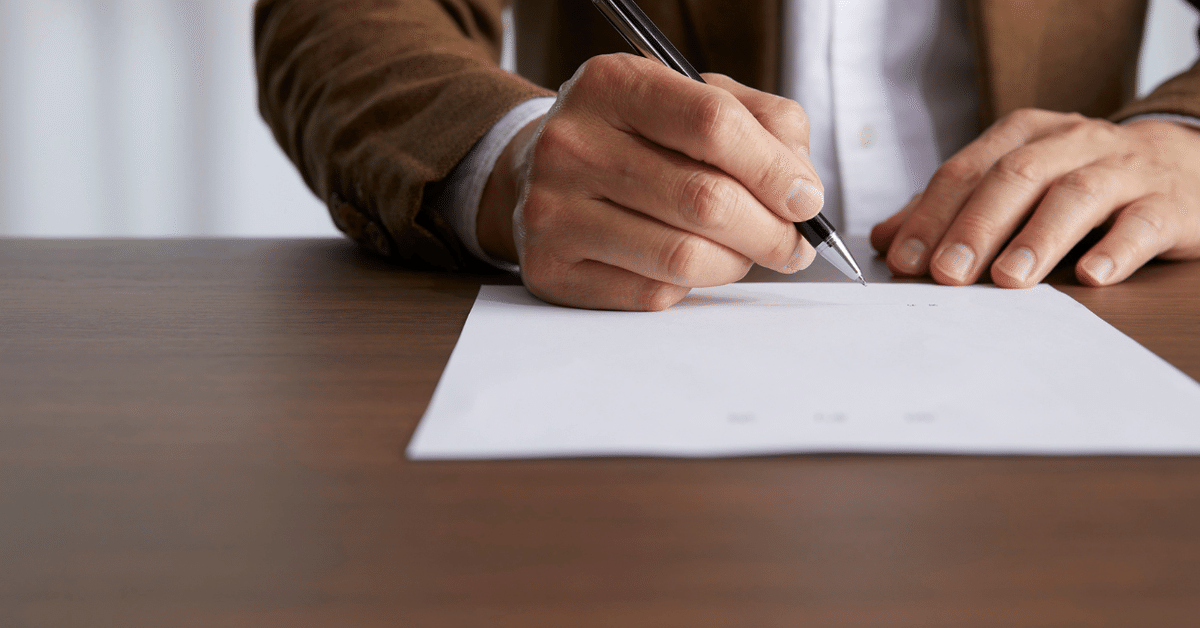
第4章│1,500円時代に備えるために
政府は
「2030年ごろまでに最低賃金1,500円を目指す」
と掲げています。
これは、単に“賃金が上がる”話ではなく、
人件費構造そのものを変えなければ
生き残れないという警鐘です。
・賃金テーブルが旧式のままでは逆転現象
(若手>中堅)
・生産性を高めないと“昇給が経営を圧迫”
→「評価制度×給与設計×業務設計」の再構築が必要
賃金の引き上げは「善意」ではなく「設計」の問題です。
信頼で人を雇い続けるために、
“割れない制度”を今から整えることが重要です。
第5章│実際の判例で見る「最低賃金割れ」の現実
①大庄事件(東京地裁 平成26年3月27日)
固定残業代を基本給に含めて支給。
実労働時間で割ると最低賃金を下回り、
未払い賃金の支払い命令。
→ 固定残業は「含める」ではなく「分けて」設計すべき。
②京橋交通事件(大阪地裁 平成27年2月25日)
歩合給と手当を合算して計算。
一部期間で割れたため、会社側に差額支払い命令。
→ 歩合・能率給も「毎月検証」しないと危険。
③小田原電機事件(横浜地裁 平成22年5月25日)
長時間労働+最低賃金割れで、
不法行為(慰謝料請求)も認容。
→ 最低賃金違反が「倫理・人格権侵害」にまで発展。
④フードサービスA社(東京労働局 令和3年度指導事例)
契約更新漏れにより旧時給のまま。
差額支給+是正勧告+指導票交付。
→ 更新ミスでも違反扱い。年1回の点検体制が必須。

裁判所は「悪意がなかった」ではなく、
「管理できなかった」点を重く見ます。
最低賃金の違反は、
経営者の注意義務違反として判断されやすいのです。
まとめ|最低賃金は「法令遵守」ではなく「信頼の最低ライン」
最低賃金を守ることは、
単なる“義務”ではありません。
従業員との信頼を守るための最低保証ラインです。
罰則や差額支払いよりも怖いのは、
“うちの会社は最低限すら守らない”という印象を残すこと。
だからこそ、
・賃金設計を整える
・契約を更新する
・管理体制を可視化する
この3点を継続的に見直すことで、
“割れない会社=信頼で選ばれる会社”へと進化できます。
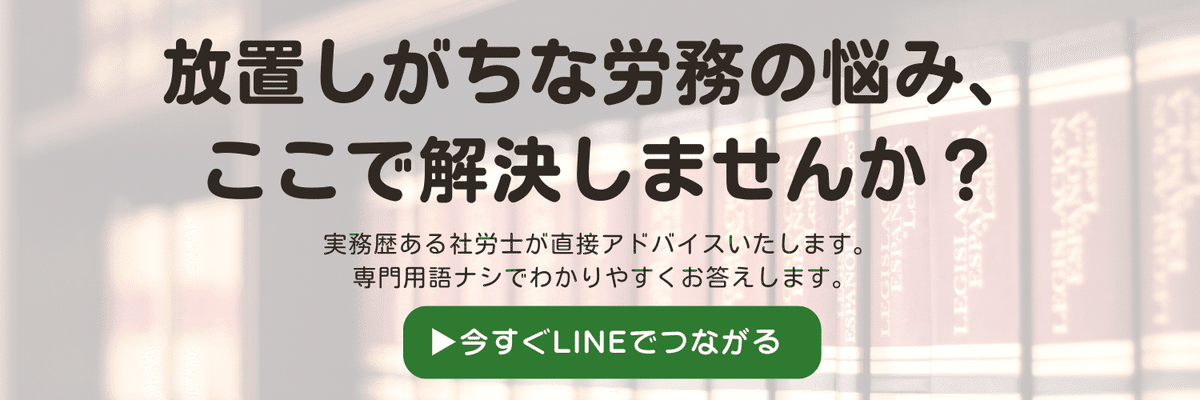
記事を読んで「この人、どんな社労士なんだろう?」と思った方は、
ぜひこちらも覗いてみてください。