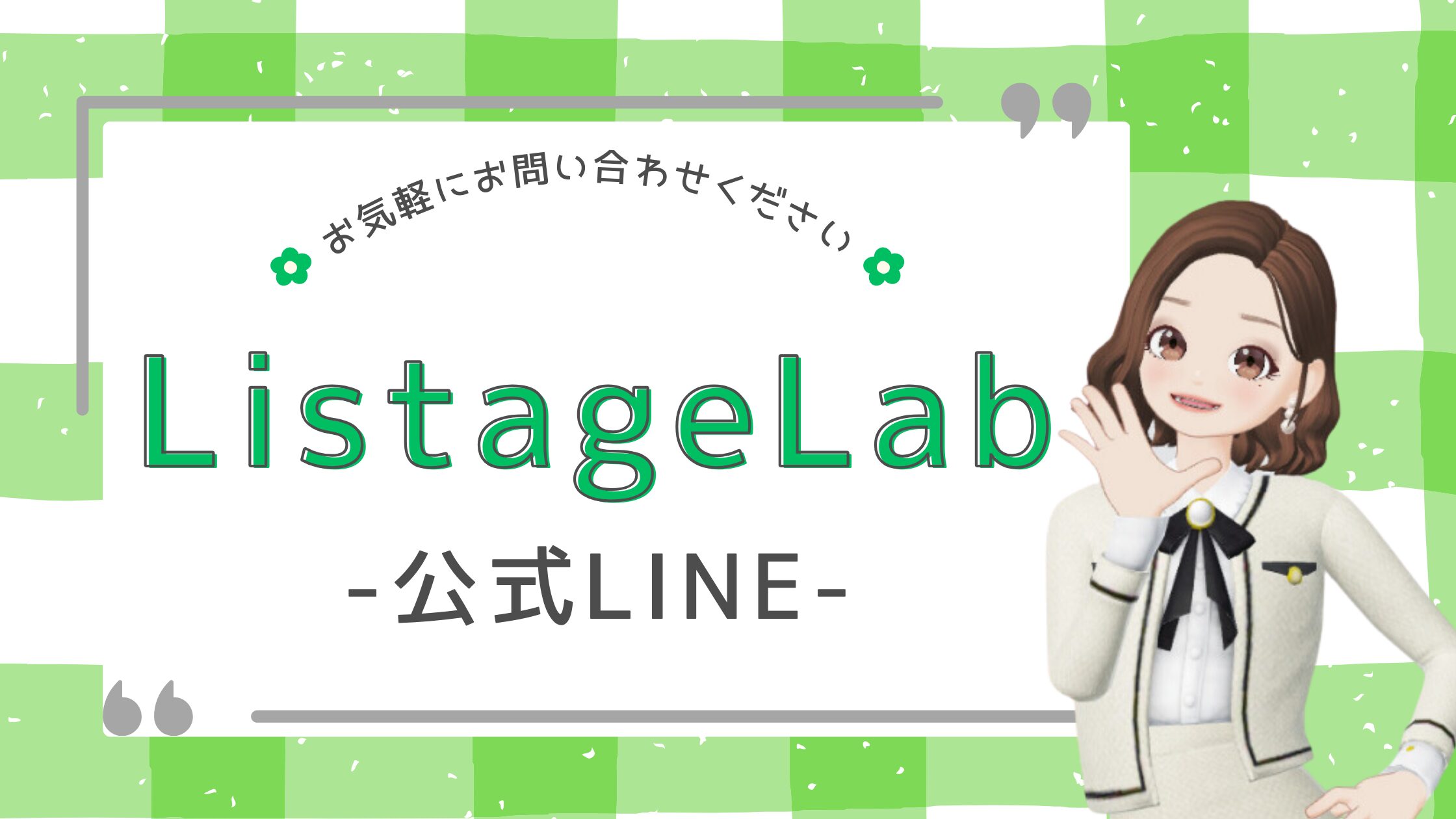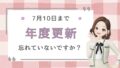目次
はじめに|経営者も気づかない“見えない地雷”
ハラスメントと聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは、「上司から部下へのパワハラ」ではないでしょうか。確かに、これまで多くの裁判事例で問題視されてきたのは、立場を利用した上からの圧力や暴言、過度な業務指示などでした。
しかし、近年増加傾向にあるのが、まさかの“逆パワハラ”。
「部下に配慮して話しても否定された」
「注意をしたら、スマホを取り出され『録音してます』と言われた」
「働き方改革って言ってますけど、これブラックですよね?」
──こんな話、今や珍しくありません。
経営者や管理職の多くは、「加害者になってはいけない」と慎重になる一方で、「部下の理不尽な言動から自分を守る手段」を持ちません。
その結果、管理職が精神的に追い詰められ、業務遂行能力を失うという事態すら発生しています。
本記事では、実際の事例や裁判例をもとに「逆パワハラ」のリアルを掘り下げ、企業としてどう備えるべきかを、社労士の視点からお伝えします。
実は増えている「逆パワハラ」事例
ケース1:注意したら「パワハラですよね?」と詰められた
ある中堅企業の営業部門で、若手社員の勤務態度が気になった上司が、軽く注意をしたところ、
「それ、パワハラじゃないですか?」と強く反論されました。
その後、本人は他の社員の前でも「僕、○○さんにパワハラされてます」と発言。職場全体がギクシャクし、上司は委縮して指導ができなくなってしまいました。
業績管理どころではなくなり、チームは一時崩壊状態に。
ケース2:「こんな働き方、ブラックじゃないですか?」
ある現場では、繁忙期で残業の協力をお願いしたところ、若手社員から「労基署に言いますよ」という一言が。
本気ではなかったにせよ、その言葉に責任者が反応して業務を調整。
結果、他の社員にシワ寄せがいき、リーダーがメンタル不調で休職。
最終的に退職となってしまいました。
裁判例から読み解く::「部下が上司を追い詰めた」ケースもある
「逆パワハラ」が法的に争われるケースはまだ少数派ですが、近年は部下の言動が上司に対する精神的損害をもたらしたと認定された民事裁判も出始めています。
たとえば、ある製造業の現場では、部下が上司の指示をことごとく無視し、社内外で「うちの上司マジで無能」と言いふらす行為が繰り返されました。
これにより上司がうつ病を発症し、最終的には休職 → 退職 → 会社提訴という流れに。
裁判所は、企業が早期に対応しなかったこと=管理責任の不履行とみなし、一定の損害賠償を命じました。
このように、「上司がパワハラをする側」という固定観念が、企業をかえって脆弱にしてしまうのです。
逆パワハラが起きる職場の特徴
1.心理的安全性が一方向に偏っている
「部下の声は尊重されるべきだが、上司の指導は制限されるべき」
──そんな風潮が強いと、管理職が過剰に萎縮し、職場は“無責任な自由空間”になってしまいます。
2.管理職が孤立している
「現場は現場でなんとかしてくれ」という放任主義のもと、管理職は相談もできず、ミスが起きれば責任だけを取らされる──そんな状況が、逆パワハラの温床になります。
3.評価制度が曖昧
成果・行動・能力を可視化する仕組みがなく、“声の大きさ”や“同調圧力”が影響力を持つ職場では、正しい指導がねじ曲げられやすくなります。
逆パワハラも企業責任になる時代
「上司が怒ったらパワハラ」
「部下が怒ったら自己主張」
このようなダブルスタンダードが続くと、組織は必ず歪みます。
さらに、逆パワハラがあっても経営層が「現場に任せているから」と放置すれば、それは“黙認”とみなされ、会社に責任が問われる可能性すらあるのです。
特に注目したいのは、「指導しないリスク」も企業責任になるという点です。
適切な注意・改善指導をしないことが、他社員への不利益や組織の機能低下につながれば、それ自体が管理不全と評価されるリスクがあるのです。
顧問社労士が介入すると何が変わるのか?
① 指導とパワハラの“線引き”を社内で統一できる
「どこまでが指導で、どこからがハラスメントなのか」を明文化し、研修や相談体制を整えることで、全社員が共通認識を持てるようになります。
② 管理職が安心して“指導できる”ようになる
「指導したら訴えられるかも…」という不安を払拭し、管理職が“正しい指導を躊躇なくできる”環境が生まれます。
③ 部下からの過度な主張に対して“冷静な対話”が可能に
外部相談窓口や顧問社労士が間に入ることで、感情的な衝突を防ぎ、対話の交通整理が可能になります。
「会社はきちんと聞いてくれる」という安心感が双方に広がります。
まとめ|「誰もが守られる職場」が企業を強くする
パワハラ=上司が悪い、という単純な構図では、現代の組織は立ち行きません。
真に機能する職場とは、上司も部下も、誰もが守られる仕組みがある場所です。
経営者が管理職を守り、管理職が部下を育てる──その循環を支えるのが、外部専門家である社労士の役割です。
「最近、現場が重苦しい」
「注意したら録音されたと管理職が萎縮している」
──そんな兆候を感じたら、社労士の出番かもしれません。
社員も、管理職も、経営者自身も守るために。
“攻めのリスク管理”としての労務顧問を、今こそご検討ください。